『とと姉ちゃん』で常子が働いた鳥巣商事は、文具を扱う会社として描かれています。
鳥巣商事は、常子が社会に出て、最初に就職した場所です。
常子はそこでタイピストとして働くことになりました。
では、鳥巣商事には実在のモデルがあるのでしょうか?
また、常子がタイピストになったのは史実通りなのでしょうか?
今回は、鳥巣商事のモデルや就職エピソードの史実との関係をくわしくご紹介します。
とと姉ちゃん鳥巣商事のモデルは?

『とと姉ちゃん』に登場する鳥巣商事には、実在のモデル会社は存在しません。
文房具を扱う企業として描かれていますが、これはドラマのオリジナル設定です。
まず、公式などからモデル企業に関する発表はありません。
さらに、昭和初期に『鳥巣商事』という文具店があったという記録も見つかっていません。
次に、常子のモデルとされる大橋鎭子(おおはししずこ)さんの史実を確認してみます。
大橋鎭子さんは、1937年に日本興行銀行へ入社しました。
当時はまだ女性の社会進出が少ない時代でした。
しかし、大橋鎭子さんは家計を支えるために就職を決意したそうです。
配属されたのは調査課で、約3年間勤務したのち、退職します。
退職の理由は、大学進学のためでした。
職場で出会った女性たちの勉強熱心な姿に感化され、自分も学びたいと考えるようになります。
その結果、『日本女子大学』へ入学する道を選びました。
ただし、大学に入学して1年も経たないうちに肺結核を発症。
体調を理由に、残念ながら中退することとなります。
このように、大橋鎭子さんの最初の就職先は文房具店ではなく銀行でした。
文房具会社に勤めたという事実も確認されていません。
つまり、鳥巣商事という会社はドラマの演出によって生まれた架空の企業と考えられます。
ただし、ドラマと史実には共通点もあることがわかりました。
常子は、鳥巣商事で約3年間働いたのち退職しました。
この『3年間の勤務』という部分は、大橋さんの実体験と一致しています。
勤務先や職種は違いますが、就職から退職までの年数は史実をもとにしている可能性があります。
とと姉ちゃんタイピストになったのは史実通り?

『とと姉ちゃん』で常子がタイピストとして働く展開は、史実とは異なります。
常子のモデルとなった大橋鎭子(おおはししずこ)さんは、過去にタイピストの経験はありません。
大橋さんの実際の職歴は以下のとおりです。
- 1937年:日本興行銀行(調査課)に入行
- 1941年:日本読書新聞の編集部に勤務
- 1946年:衣装研究所を設立
どの職場でも、タイピストとしての経験は確認されていません。
つまり、常子がタイピストとして働いたのはドラマオリジナルの設定であることがわかります。
ではなぜ、ドラマでは常子がタイピストになったのでしょうか。
調べてみると、昭和初期の日本でタイピストは女性に人気の職業でした。
専門的なスキルが求められる一方で、安定した収入と社会的地位を得られる仕事でもあったのです。
ドラマでは、常子は鞠子の大学進学費を稼ぐために働き始めます。
そのため、一定以上の収入がある職業に就く必要がありました。
高収入を得られるタイピストは、物語上もリアリティのある選択肢だったのでしょう。
また、タイピストは女性の社会進出や自立を象徴する職業として、取り入れやすかったと考えられます。
机に向かって仕事をする姿は、映像としても描きやすく、昭和の時代背景にも合っていました。
当時は『看護師』『美容師』『電話交換手』なども人気がありました。
その中で、常子のキャラクターや物語に一番合っていたのが、タイピストだったのかもしれません。
結論として、常子がタイピストになったのは史実通りではなく、ドラマの創作部分です。
史実とは異なりますが、時代背景とドラマの物語性を反映した選択だったのではないでしょうか。
なお、今後新しい情報が明らかになれば、こちらの記事もあわせて更新いたします。
まとめ
- 鳥巣商事は実在せず、ドラマのオリジナル会社
- 常子がタイピストになる展開も史実ではない
- モデルの大橋鎭子さんは銀行と新聞社で勤務
- タイピストは昭和初期に女性に人気の職業
- ドラマは時代背景と物語性を重視して構成された
朝ドラ『とと姉ちゃん』に登場する『鳥巣商事』は、実在しないことがわかりました。
また、常子が『タイピスト』として働く描写は、実在のモデルに基づいているわけではありません。
常子のモデルである大橋鎭子(おおはししずこ)さんは、昭和12年に日本興行銀行に就職。
その後は、新聞社を経て衣装研究所を設立しました。
大橋鎭子さんが文房具店に勤めた事実も、タイピストとして働いた経験も記録されていません。
つまり、鳥巣商事やタイピストのエピソードは、物語をよりドラマチックにするための創作です。
ではなぜ、あえてこうした職業が描かれたのでしょうか。
昭和初期の日本では、タイピストは女性に人気のある職業でした。
専門性が求められ、一定の収入があり、社会的な評価も得られる仕事だったからです。
ドラマでは、常子が妹の学費を稼ぐために就職します。
そのため、リアリティをもたせつつ高収入の仕事として『タイピスト』が選ばれたと考えられます。
また、タイピストという職業は、女性の社会進出や自立を象徴する存在でもありました。
そういった意味でも、当時の時代背景を映し出す役割を果たしていたのでしょう。
当時の女性たちの生き方や働き方を描くための演出としては非常に効果的だったと言えます。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
【関連記事】
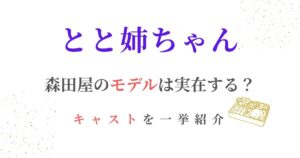
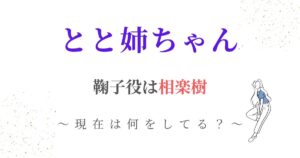
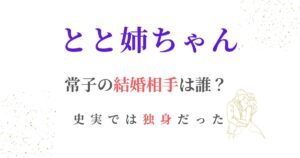
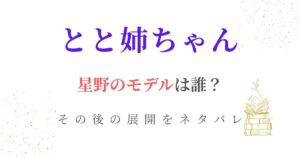
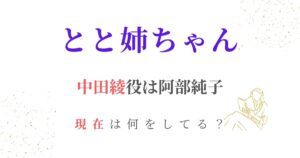
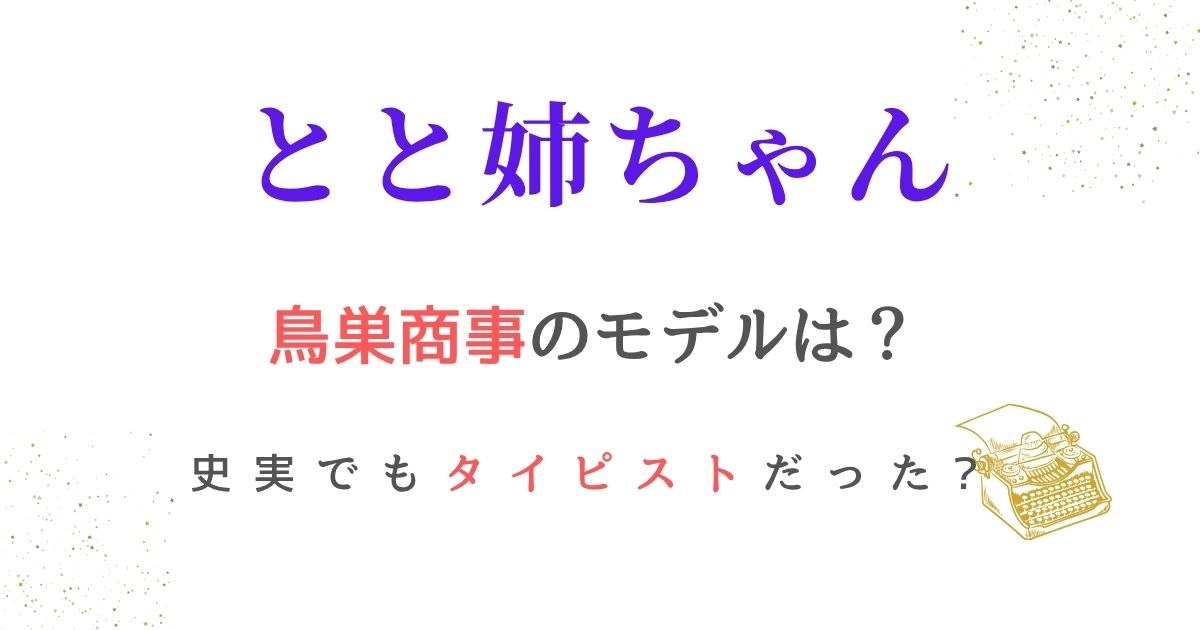
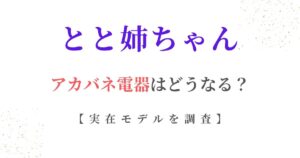
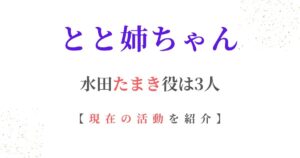
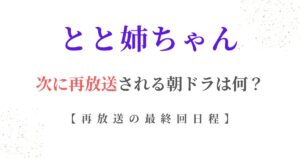
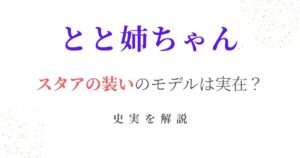
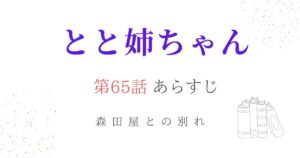
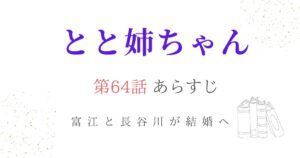
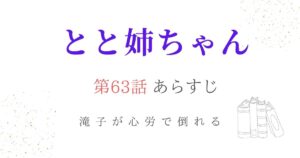

コメント