『ばけばけ』で、トキの家は『没落士族(ぼつらくしぞく)』として描かれています。
第1話から父親はすでに無職で、家族の生活は苦しい状況。
物語は、この厳しい現実から始まります。
では『没落士族』とは何を意味するのでしょうか。
今回は、没落士族の意味とその歴史的な背景をわかりやすく解説します。
【ばけばけ】没落士族とは?
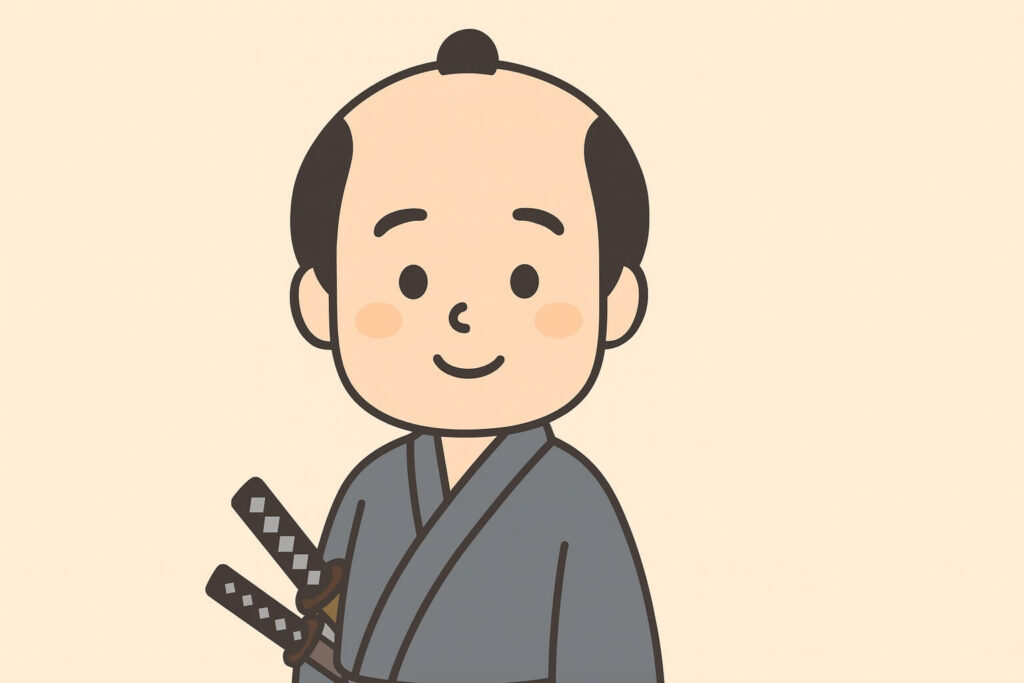
没落士族(ぼつらくしぞく)とは、明治維新で暮らしに困った元武士の家族のことです。
『ばけばけ』の主人公トキの父と祖父も、もとは武士でした。
しかし、明治維新のあとに『士族』と呼ばれるようになります。
では、この『士族』とはどんな人々を指すのでしょうか。
ここからは、士族の意味と没落士族が生まれた背景を解説します。
士族とは?
士族とは、明治維新後に武士の身分を引き継いだ人々のことです。
江戸時代の侍は、明治になると『士族』と呼ばれました。
『ばけばけ』のトキの父や祖父も、その士族にあたります。
もともと武士は幕府や藩から給料をもらって暮らしていました。
しかし明治の改革で、その特権は失われてしまいました。
没落士族が生まれた理由
没落士族が生まれた理由には、明治維新の社会変化があります。
主な理由は次の3つです。
- 武士の特権がなくなった
- 秩禄処分で給料が打ち切られた
- 新しい仕事に馴染めなかった
武士の特権がなくなった
江戸時代まで武士は身分が高く、収入や役職も保証されていました。
しかし、明治維新で身分制度がなくなります。
その結果、武士だけの特権は廃止されることになりました。
秩禄処分で収入を失った
武士は『俸禄(ほうろく)』と呼ばれる給料をもらっていました。
明治政府は財政難のため、俸禄を打ち切る『秩禄処分』を実施。
代わりに『公債』という国の借金の証書を渡しました。
しかし、利子はわずかしかもらえず、家族の生活を支えるには足りませんでした。
その結果、多くの士族が生活に困ることになりました。
新しい仕事に馴染めなかった
一部の士族は軍人や官僚になれましたが、それは少数派。
農業や商売を始めた人もいましたが、経験がなく失敗する例が多かったのです。
さらに武士としての誇りから、時代に合わせて変化できない人もいました。
こうして生活の基盤を失った人々が『没落士族』と呼ばれるようになりました。
【ばけばけ】トキの父がなぜ無職か時代背景を解説

トキの父が無職であったのは、没落士族の姿を体現していると考えられます。
『ばけばけ』第1話では、すでに父は職を失った状態で登場します。
時代設定は1876年ごろ。
ちょうど秩禄処分によって士族が収入を絶たれていた時期にあたります。
武士の誇りと現実
トキの父と祖父は武士としての誇りを強く持っていました。
しかし明治になると、侍の特権はなくなりました。
給料も打ち切られます。
それでも、父や祖父は誇りを手放せません。
まげを切ることも、新しい職につくこともできませんでした。
その結果、無職のまま家族を抱えることになったのです。
史実との関係
トキの父は、まさに典型的な没落士族として描かれています。
これは創作ではなく、史実にもとづいた設定です。
モデルとされる稲垣金十郎さんも『没落士族』でした。
明治維新後に職を得られず、新しい事業に挑戦しましたが失敗。
経済状況は悪化し、家を追われるほど困窮したと伝えられています。
『ばけばけ』では、この史実がアレンジされ、物語に反映されているのです。
まとめ
没落士族とは、明治維新で特権や収入を失い、生活に困った士族のことです。
明治維新後、武士の特権は廃止。
秩禄処分で給料も打ち切られました。
さらに、新しい仕事に馴染めなかったことも没落の理由でした。
朝ドラ『ばけばけ』では、主人公トキの父がその典型として描かれています。
誇りを守ろうとしながらも職を得られず、無職のまま家族を抱えて苦しむ姿。
まさに没落士族そのものを体現しています。
史実でも同じことが起きていました。
モデルとされる稲垣金十郎さんも、事業に失敗し、家を失うほど困窮したのです。
ドラマはこの史実をアレンジして、物語に反映させています。
つまり、トキの父が無職だったのは偶然ではありません。
時代に翻弄された士族の現実が描かれているのです。
そして、没落士族であるがゆえに、トキは家族を支える立場となります。
トキがどのように家族を守っていくのか。
今後の物語の大きな注目ポイントとなりそうです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
【関連記事】
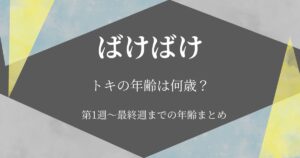
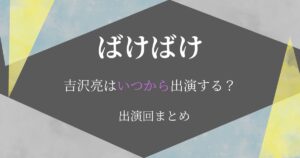
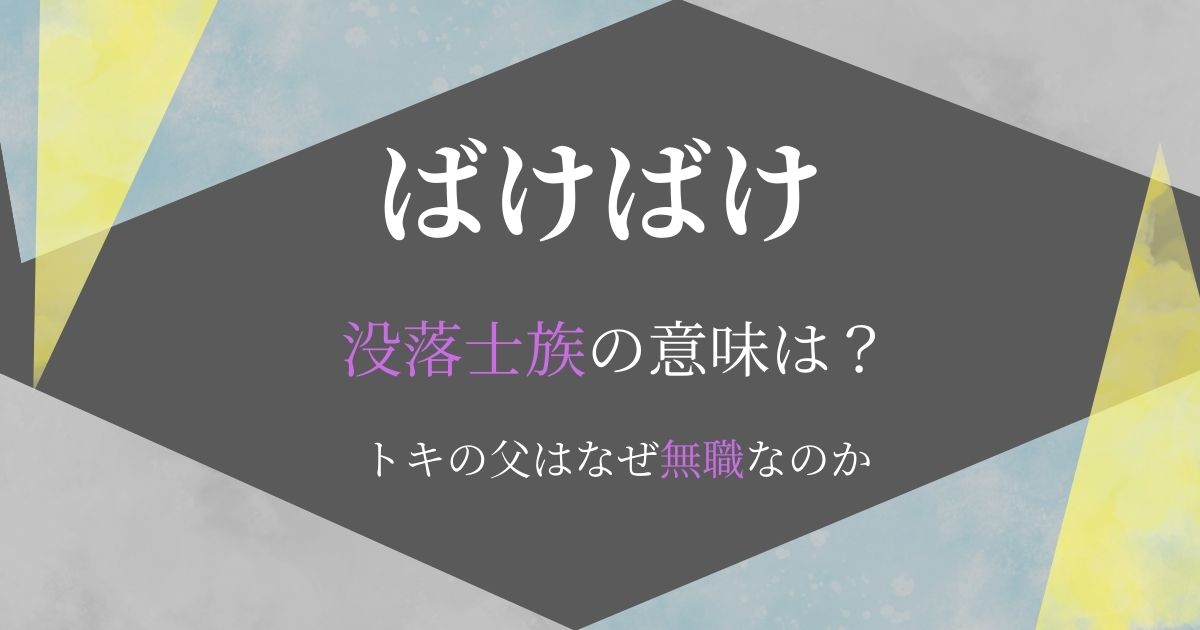
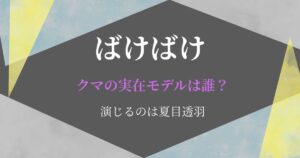
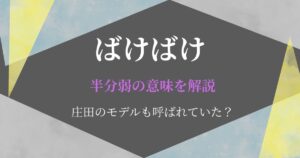
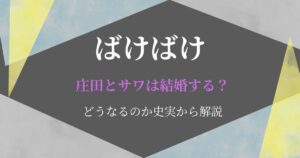
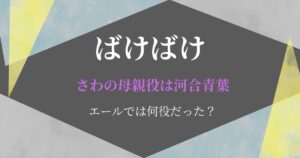
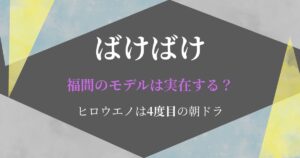
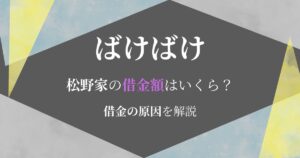
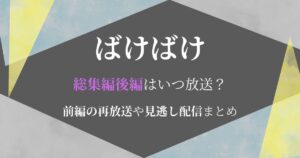
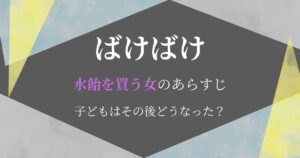
コメント