『あんぱん』で黒井先生が放った印象的な台詞に、ボウフラという言葉が登場しました。
では、この『ボウフラ』とは、何を意味していたのでしょうか。
今回は『ボウフラ』という言葉の意味や意図を解説させていただきたいと思います。
また、女子師範学校の厳しさや、当時の教育観についても調べてみました。
あんぱんでボウフラの意味は?
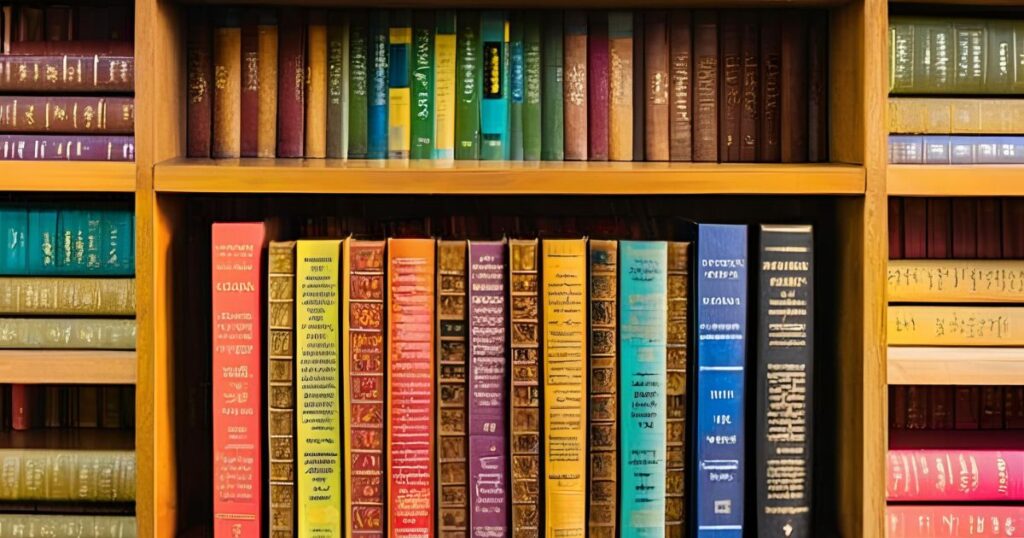
あんぱんで、黒井先生が台詞に何度も登場した『ボウフラ』。
ボウフラとは、蚊の幼虫のことを指します。

まさか、うさ子を蚊の幼虫に例えるとは思いませんでした。
文字通りの意味は蚊の幼虫ですが、物語ではそれ以上の意味が込められていました。
どの場面で使われ、どんな気持ちが込められていたのか。
ひとつずつ見ていきましょう。
情けなさ過ぎる



あなたは弱すぎる、鏡川のボウフラよりも弱い。
『鏡川のボウフラよりも弱い』は、情けなさ過ぎるという意味だと考えました。
これは、あんぱん第5週で黒井先生がうさ子に向かって投げかけた台詞です。
鏡川は、高知県に実際に存在する川の名前。
そこにいる『ボウフラ』は、弱く非力な生き物です。
黒井先生の台詞をそのまま受け取ると『鏡川にいる蚊の幼虫よりも弱い』という意味に。
ボウフラは、水面近くでひょろひょろと泳ぐ、か弱い存在。
蚊の幼虫よりも弱いか弱いなんて、あまりに情けなさ過ぎる。
黒井先生からうさ子に対する、強烈な否定の感情が込められた台詞だと感じました。
黒井先生の言葉には、厳しさと同時に奮起を促すような思いも込められていたのではないでしょうか。
覚悟や責任感が足りない



立て、立ちなさい、ボウフラ!
こちらも5週、黒井先生がうさ子に対して言った台詞です。
このボウフラは、うさ子に対する呼び名。
また『未熟で覚悟が足りない存在』という意味で伝えた台詞だと感じました。
薙刀も授業で周囲よりも一歩遅れをとっていたうさ子。
立ち上がることも出来ないうさ子を黒井先生は『自分で立ち上がれ』と叱咤しました。
まだ精神的に未熟なうさ子に自分で立ち上がって欲しい。
自分の未熟さを受け止め、覚悟や責任感を持って一歩踏み出して欲しい。
そんな黒井先生の強い覚悟や願いが台詞に込められているよう思います。
この言葉には、精神的な強さや覚悟、責任感を持って成長して欲しい。
そんな教育者としての強い願いが込められているように感じました。
弱くて守るべき存在



朝田のぶ、あなたは実に弱い。ボウフラを守ることさえできない。
こちらも同じく第5週で黒井先生がのぶに対して伝えた言葉でした。
このボウフラは『弱い存在』、つまり弱くて守るべき存在の人を指していると感じました。
黒井先生に叱られたうさ子をかばおうとしたのぶ。
黒井先生と薙刀の仕合をしますが、すぐに弾かれ、逆に攻撃されてしまいます。
黒井先生は、のぶ自身も未熟で弱く、もっと弱い存在も守れない。
そして、将来教師になるなら人を守らなければならないと厳しく指摘。
表面的な叱責だけではなく、教師としての資質を問い直す真剣な思いを感じました。
あんぱんで女子師範学校が厳しかった理由とは


『あんぱん』で、女子師範学校は非常に厳しい場所として描かれています。
では、なぜ女子師範学校はあんなに厳しかったのでしょうか。
その背景には、3つの理由がありました。
- 将来の教師として品行方正が強く求められた
- 女性の社会進出をかけていた
- 国の教育政策と結びつき
以上3つが、女子師範学校が厳しかった理由だと考えました。
品行方正が強く求められた
女子の模範として、品行方正が強く求められたことが理由だと考えました。
女子師範学校は、女性教師を育てる教育機関です。
生徒達は卒業後、子ども達の前に立ち、教育を担うことになります。
そのため、誰よりも『模範的な存在』であることが求められました。
女性が人前に立ち、社会にでること自体が珍しかった時代。
その分、社会からの期待や監視の目も強く、自然と厳しくならないといけない。
そのため、誰よりもきちんとしていることが求められました。
女性でありながら、人前に立ち、社会に出る。
当時としては、非常に大きな責任が求められていたのです。
そのため、学校側も社会からも目が厳しく、厳しく育てられたのだと思いました。
女性の社会進出をかけていた
『良妻賢母』という言葉が重んじられていた時代。
女性が学問をすることは、珍しく批判されがちなことでもあったのです。
そして、社会的な挑戦でもありました。
女子師範学校の生徒は家庭ではなく、外で教壇に立つ。
時代の最前線を歩く、これからの時代のロールモデル的な存在だったと考えられます。
成功した場合、女性も社会で活躍することができる。
一方で、失敗した場合は、女性には無理だったと判断されてしまうかもしれない時代。
女性の社会進出をかけ、失敗が許されない、緊張感のある教育が行われていました。
国の教育政策との結びつき
女子師範学校は、国の教育政策との結びつきが強かったと考えられます。
教育こそが国を作ると考えられていて、優秀な小学校教員を育てることは最重要課題でした。
そのため、学校は基本的に国費(税金)で運営されていました。
学費も無料で、寮費なども一部支給されるなど、かなり手厚い待遇だったのです。
しかしその分、成果が求められます。
税金で学ばせてもらっているという、強い責任ものしかかっていました。
良き教師にならなければいけない。
そんな国からのプレッシャーもあったのだと思います。
生徒たちは以下のような理想像を押しつけられていたのです。
- 成績優秀
- 礼儀正しく、人間性も優れている
- 精神的にも肉体的にも強い
女子師範学校は『教師の訓練機関』であると同時に『国の未来担う存在』場でもあったのです。
まとめ
- ボウフラは、蚊の幼虫の意味
- 女子師範学校の厳しさは、時代背景や社会的使命が関係していた
『あんぱん』で登場した、ボウフラという言葉。
そのままでは、蚊の幼虫という意味になります。
しかし、黒井先生の教育者としての真剣な想いが込められたいた言葉でした。
また、女子師範学校の厳しさも時代背景や社会的使命が強く関係していたことが判明しました。
弱い存在だったうさ子やのぶが、どう成長していくのか。
今後の展開が楽しみです。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
【関連記事】
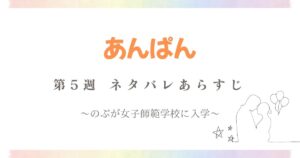
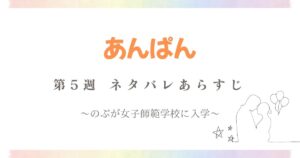
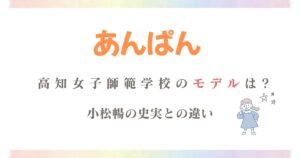
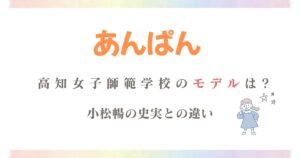
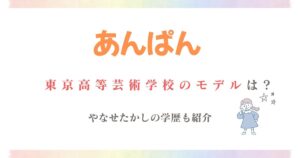
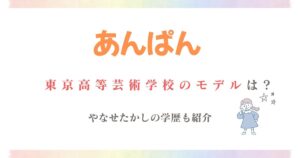
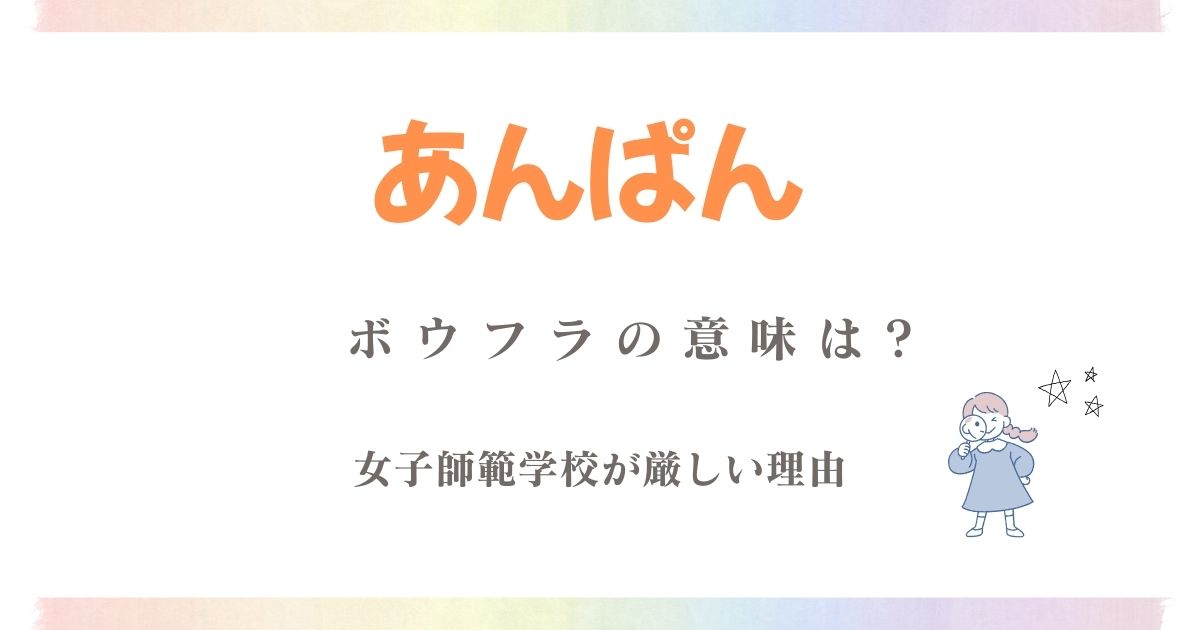
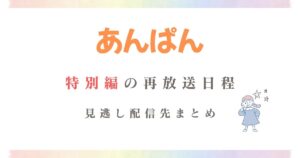
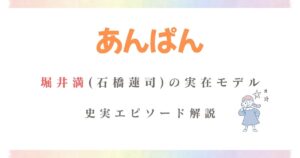
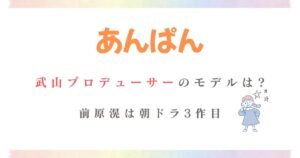
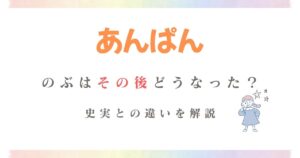
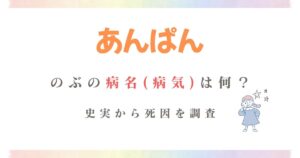
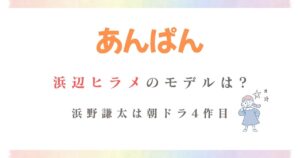
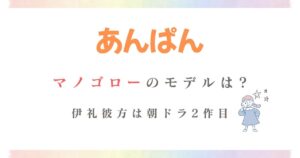
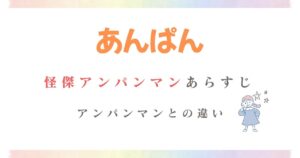
コメント